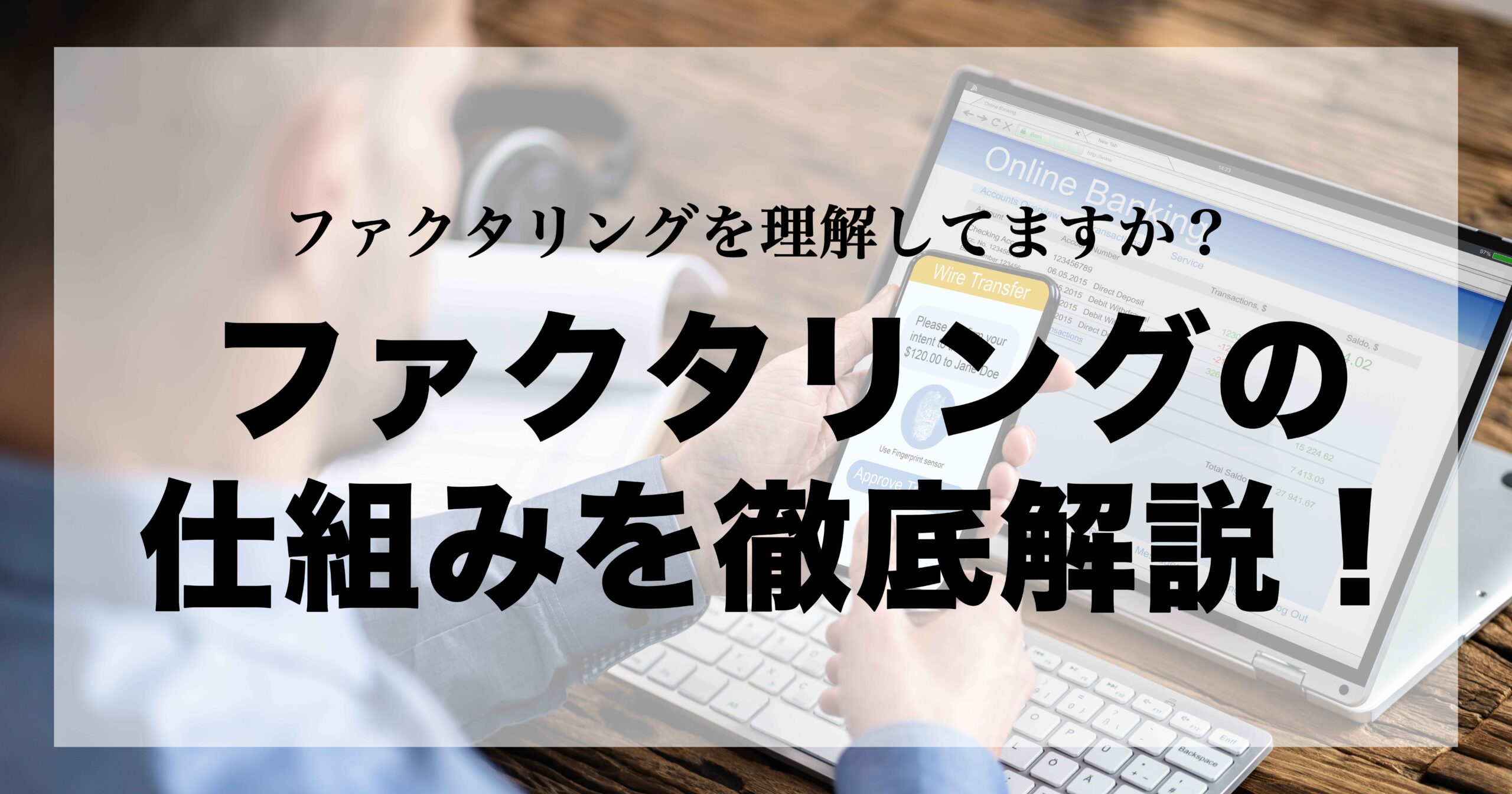資金繰り改善の手段として注目されるファクタリング。
しかし「ファクタリングを利用すると、会社の信用力は上がるのか?」という疑問を持つ経営者は少なくありません。特に金融機関との取引や今後の融資を見据えている場合、この点は非常に気になるところです。
この記事では、ファクタリングが信用力に与える影響、金融機関の見方、誤解されやすい点、実務上の注意点、そして士業による支援の可能性について、わかりやすく解説します。
ファクタリングを使っても会社の信用力は基本的に「上がらない」
結論から言えば、ファクタリングを利用したからといって、会社の信用力が直接的に「上がる」ことはありません。
ファクタリングはあくまで「既に発生している売掛金を資金化する手段」であり、企業の収益性や財務体質が良くなるわけではないからです。むしろ、状況によっては「資金繰りが厳しいのでは?」と見られ、信用力にマイナスの印象を与えることもあります。
ファクタリング即日といってもその点は注意が必要です。
信用力に影響する要素とファクタリングの関係
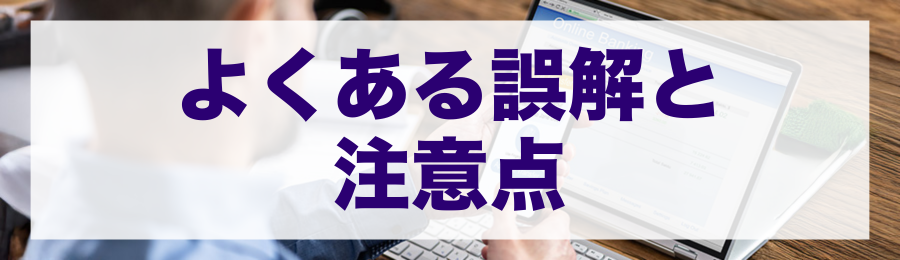
信用力(与信)は、主に以下の要素から判断されます
- 売上や利益の安定性
- 自己資本比率や負債比率
- キャッシュフローの健全性
- 税金・社会保険の納付状況
- 取引履歴や信用情報
ファクタリングは貸借対照表上、借入金とは異なる処理(売掛金の譲渡)となるため、厳密には負債としてカウントされません。ただし、金融機関や取引先からの見え方によっては、「短期的な資金繰り対策が必要な状態」と見なされるリスクがあります。
誤解されやすい点:借金ではない=信用力に影響しない?
「ファクタリングは借金ではないから信用には関係ない」といった説明をする業者もいますが、これは正確ではありません。
確かに帳簿上は借入金ではありませんが、金融機関などの与信判断においては「ファクタリングの利用履歴」も含めて、企業の資金調達手段としての健全性をチェックされます。特に頻繁にファクタリングを利用している場合は、構造的な資金繰りの問題が疑われることがあります。
実務での注意点:取引先や金融機関にどう見られるか
2社間ファクタリングを利用する場合、売掛先に知られないのがメリットですが、逆に社内や取引先に隠れて利用することで、後に発覚した際の信頼失墜にもつながりかねません。
また、3社間ファクタリングでは取引先に直接通知が行くため、「資金に困っているのでは?」と誤解される可能性もあります。こうした外部評価リスクを踏まえたうえで、慎重に導入を検討する必要があります。
士業によるサポート:信用力維持とファクタリング活用の両立
行政書士、税理士、弁護士などの専門家は、ファクタリングの導入支援だけでなく、会社の信用力を損なわない活用方法についてもアドバイスが可能です。
たとえば、
- 財務改善計画と連動した資金調達アドバイス
- 与信に配慮した契約内容のチェック
- 金融機関への説明資料作成支援
- 不当な契約や高額手数料からの保護
こうした専門的支援を活用することで、信用を落とすことなく、必要な資金を調達することができます。
即日ファクタリングも参考にしつつ決めると良いでしょう。
まとめ:信用力アップには根本的な経営改善が必要
ファクタリングは一時的な資金調達手段であり、それ自体が会社の信用力を上げるものではありません。むしろ、頻繁な利用や不透明な契約は逆効果となる可能性もあります。
信用力を本質的に高めたいのであれば、売上の増加、利益の確保、財務体質の改善といった地道な経営努力が必要です。そして、必要に応じて士業などの専門家と連携し、リスクのないファクタリング活用を目指しましょう。